過去の講演会(2024年度~)経済研究所
2025年度 講演会等のお知らせ及び開催報告
本年も恒例の公開講演会「公認会計士への道」(公認会計士制度説明会)を2025年4月23日(水)午後7時より、本学池袋キャンパス8号館2階8202教室において、対面とオンラインのハイブリッドで開催した。対面は15名程度の参加者であったが、オンラインを併せると延べ50名以上の参加者を得た。

羽山友紀子氏の講演
まず、司会(小澤)及び蓮見雄経済研究所長(本学経済学部教授)のあいさつの後、日本公認会計士協会東京会広報委員会委員で、本学文学部フランス文学科卒業された羽山 友紀子氏(公認会計士)から公認会計士制度の説明があった。羽山氏は「公認会計士の仕事と魅力」と題して、公認会計士の使命、監査・税務・コンサルティング・企業内会計士といった公認会計士の専門分野と活躍フィールド、試験制度の概要等についてお話くださった。また最後に現役公認会計士の声として、公的な団体や非営利団体にも監査業務が拡大していることや、海外での活躍の機会、女性公認会計士の活躍、AI時代の公認会計士業務等、いかに公認会計士が魅力的な仕事であるかについてご説明いただいた。

佐々木登那氏の講演
次に、合格体験談として、公認会計士試験に本学経済学部会計ファイナンス学科在学中に合格し、2025年3月に本学を卒業され、現在、有限責任あずさ監査法人に勤務されている佐々木登那氏からお話しいただいた。特に、公認会計士を知ったきっかけ、大学生活と資格試験勉強の両立、試験勉強の仕方、試験合格後の日常など、具体的かつ的確に説明があった。また、佐々木氏からは、公認会計士試験にチャレンジする後輩たちに向けてメッセージが送られた。

山田浩一氏の講演
最後に山田浩一氏(公認会計士・立教公認会計士会会長)から、ベテラン公認会計士としての視点から、公認会計士という職業の魅力についてお話があった。この仕事の未来は明るく、ぜひともこの試験にチャレンジしてほしいとの激励をいただいた。
講演会終了後には、対面参加の学生とオンライン参加の学生から、多くの質問が寄せられた。予定時間を大幅に超過したが、講師の先生方には質問に真摯にお答えいただいた。本年度も後輩のために貴重なお時間を割いて本学までお越しいただいた講師の先生方と日本公認会計士協会東京会各位には、改めてお礼申し上げたい。
2024年度 講演会等のお知らせ及び開催報告

会場の様子
【日時】2025年3月8日(土)14:00~17:30
【会場】池袋キャンパス 8号館8303教室
【参加人数】120名
【報告】
1.山本 周吾氏(本学経済学部准教授)
「日本経済における生産性と賃金・物価の相互連関:金融緩和政策の波及経路の整理」
2.山口 義行氏(本学名誉教授)
「『ぬるま湯資本主義』の終焉と日本経済」
3.金子 勝氏(本学経済学部特任教授)
「アベノミクスの罪と罰」
【会場】池袋キャンパス 8号館8303教室
【参加人数】120名
【報告】
1.山本 周吾氏(本学経済学部准教授)
「日本経済における生産性と賃金・物価の相互連関:金融緩和政策の波及経路の整理」
2.山口 義行氏(本学名誉教授)
「『ぬるま湯資本主義』の終焉と日本経済」
3.金子 勝氏(本学経済学部特任教授)
「アベノミクスの罪と罰」
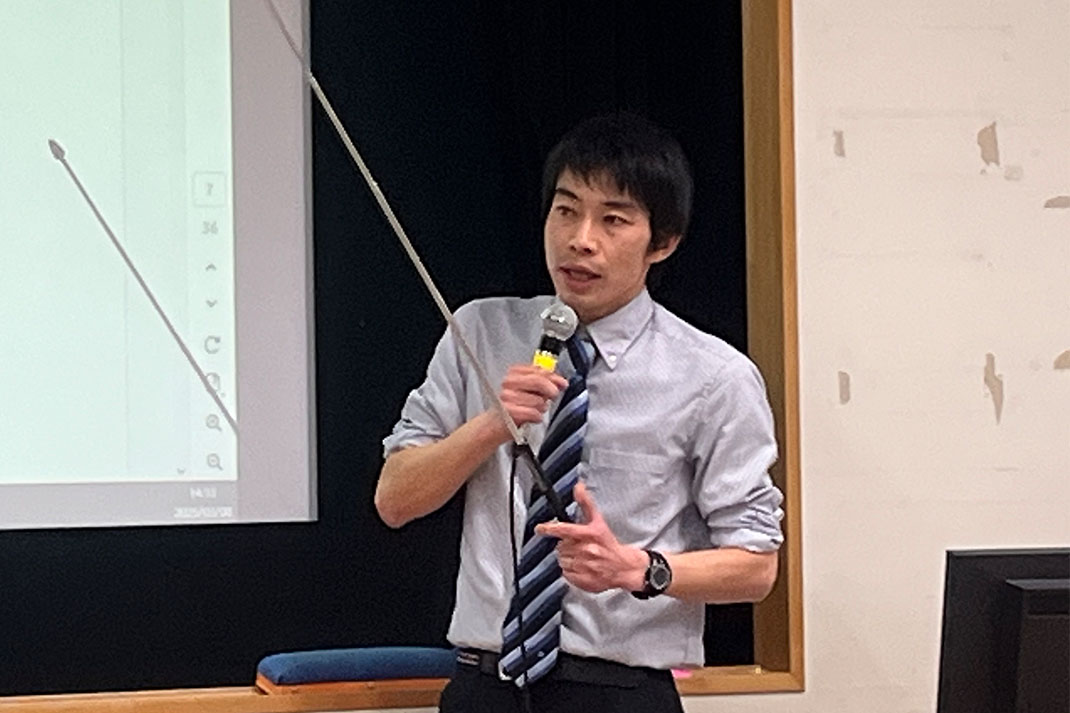
第1報告 山本周吾氏(本学経済学部准教授)
山本周吾報告は、①豊かさを実感するためには実質賃金の上昇が必要であるが、そのためには、生産性と収益の向上が必要ある。②コロナ禍以前、日銀がアクセル全開で金融緩和をしたが、デフレから脱却できなかったのは、構造的な問題も原因があるのではないか。③そのためにバラッサ・サミュエルソン効果に注目し検討を加える。④また、近年のデフレに関する先行研究をサーベイする。その中では、「価格マークアップ」と「賃金マークダウン」について検討を加える。⑤さらに、金融政策・金融問題と絡めて論じる必要があるので、投資、そのなかでも無形資産に注目して分析を加える。⑥上記の内容を、産業構造を考慮して、先行研究を紹介しつつ、生産性、賃金、価格の関係を明らかにした。
結論としては、金融政策の経路について①「理想の波及経路」が考える有形・無形資産の向上による生産性・賃金・価格の上昇とは異なり、「実際の波及経路」では、大企業・貿易財産業(のみ)に恩恵がもたらされる構造になっていること。②日銀ができることはベースマネーの供給と政策金利の調整くらいしかないこと。③しかし、実体経済の内部における資金配分までは、日銀は管理することが難しいこと。④ 以上より、日本経済では産業構造や、金融仲介機能にも問題があり、日銀だけで対処できなかった可能性があること。⑤ただ、コロナ禍以降、円安や人手不足を通じたインフレ圧力で状況変わりつつあるのではないかというものであった。
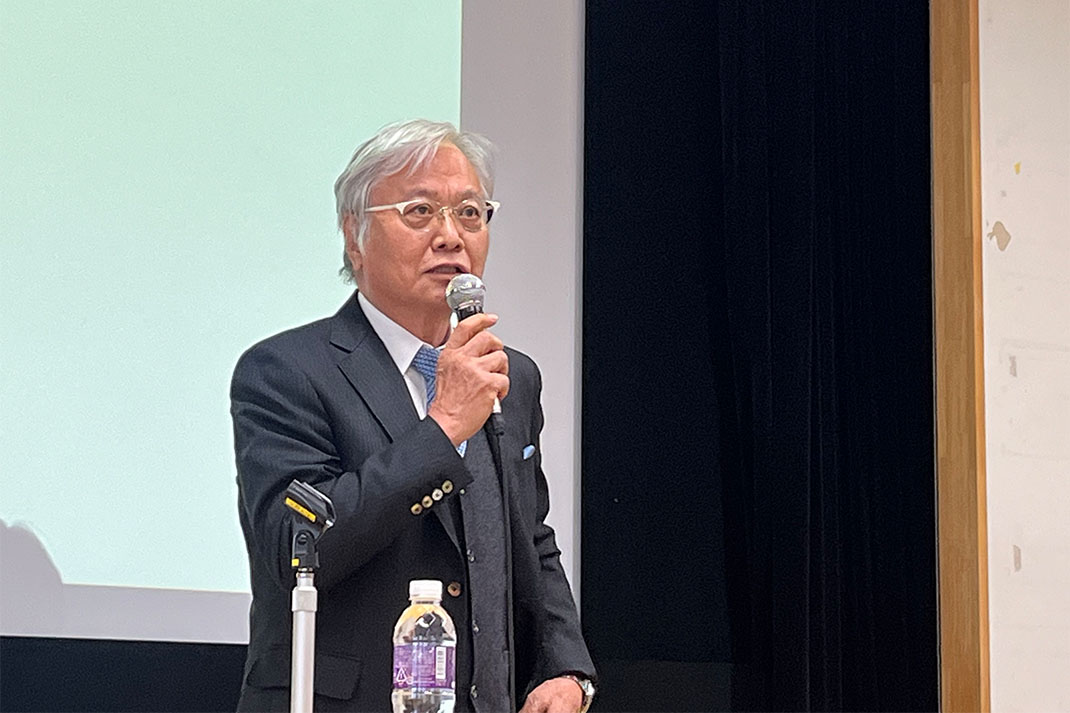
第2報告 山口義行氏(本学名誉教授)
山口義行報告は2014年に安倍・黒田路線がスタートしたが、その帰結は、①低金利⇒活況なき倒産減、①低金利⇒活況なき倒産減、①低金利⇒活況なき倒産減であったことを明らかにした。そして、この現象こそ、「ぬるま湯資本主義の成立」させたという。
特に、中小企業を取り巻く環境の厳しさが顕著である。それは①物価高による仕入れコストの上昇、②前代未聞の人手不足、③技術革新に伴う仕事の喪失、④金利上昇による資金調達コストの上昇がからも明らかだという。従って中小企業は、ぬるま湯資本主義は終わったと考え、覚悟を決めて自己変革に挑まなければならない。そのために中小企業が目指すべきは、①より効率的な会社になる、②価値創造・顧客創造をより強力に推進できる会社になる、③人を引き寄せられるより魅力的な会社になることだ。その時重要なのは、こうした課題を達成すべく「新しい考え方」に立ち、「新しい仕組み」を構築することだ。それは、質的変化を遂げることでもあり、それを再定義しなければならないという。山口報告は自己変革に挑戦する企業の実例を紹介しながら、社会は再定義に時代に入ったと結論づける。
特に、中小企業を取り巻く環境の厳しさが顕著である。それは①物価高による仕入れコストの上昇、②前代未聞の人手不足、③技術革新に伴う仕事の喪失、④金利上昇による資金調達コストの上昇がからも明らかだという。従って中小企業は、ぬるま湯資本主義は終わったと考え、覚悟を決めて自己変革に挑まなければならない。そのために中小企業が目指すべきは、①より効率的な会社になる、②価値創造・顧客創造をより強力に推進できる会社になる、③人を引き寄せられるより魅力的な会社になることだ。その時重要なのは、こうした課題を達成すべく「新しい考え方」に立ち、「新しい仕組み」を構築することだ。それは、質的変化を遂げることでもあり、それを再定義しなければならないという。山口報告は自己変革に挑戦する企業の実例を紹介しながら、社会は再定義に時代に入ったと結論づける。
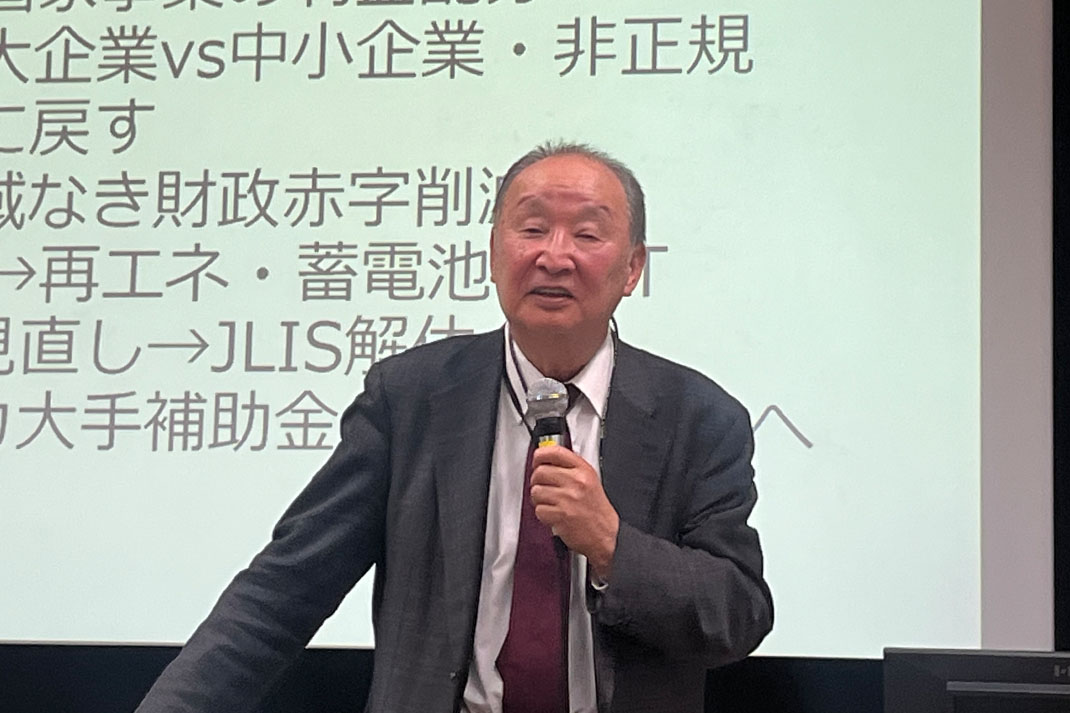
第3報告 金子勝氏(本学経済学部元特任教授)
金子勝報告は、アベノミクスは①デフレ脱却に失敗したこと。②アベノミクスの結果は、経済成長ができず、産業衰退と貿易赤字を引き起こし、内部留保膨張と実質賃金低下し、地方と人口減少が起きた。③利益政治と腐敗を生み出し(ルールと規律の崩壊)、隠れた防衛費膨張を引き起こしていることを明らかにした。
問題は、アベノミクス失敗の総括をしないばかりか、赤字国債に依存するあまり円安インフレが起きていること。実質賃金低下と社会保障が削減されることにより消費が伸びないこと。歳出の中身を問わないため、知識経済化、ジェンダー、少子化対策がおくれていること。さらに、フェイクファシズムの危険性が増していること。そして、最も重要なことはこのまま減税ポピュリズムが続けば日本を滅ぼすことになるというものであった。
問題は、アベノミクス失敗の総括をしないばかりか、赤字国債に依存するあまり円安インフレが起きていること。実質賃金低下と社会保障が削減されることにより消費が伸びないこと。歳出の中身を問わないため、知識経済化、ジェンダー、少子化対策がおくれていること。さらに、フェイクファシズムの危険性が増していること。そして、最も重要なことはこのまま減税ポピュリズムが続けば日本を滅ぼすことになるというものであった。
【日時】2024年11月6日(水)18:00~20:30
【会場】池袋キャンパス 太刀川記念館3階カンファレンスルーム(オンライン併用)
【参加人数】95名
【報告】
1.スティナ・ヴァング・イリアス氏(中央職業訓練委員会委員長)
「デンマーク職業訓練の諸委員会とアクター」
2.トマス・フェラン氏(デンマーク労働組合連合、職業教育訓練政策コンサルタント)
「労働組合からみたデンマークの職業訓練制度と労働市場モデル」
3.アント・ヴェスタゴー・ロウ氏(オルボー大学准教授)
「デンマークのデュアルモデル 学校と現場実習」
【会場】池袋キャンパス 太刀川記念館3階カンファレンスルーム(オンライン併用)
【参加人数】95名
【報告】
1.スティナ・ヴァング・イリアス氏(中央職業訓練委員会委員長)
「デンマーク職業訓練の諸委員会とアクター」
2.トマス・フェラン氏(デンマーク労働組合連合、職業教育訓練政策コンサルタント)
「労働組合からみたデンマークの職業訓練制度と労働市場モデル」
3.アント・ヴェスタゴー・ロウ氏(オルボー大学准教授)
「デンマークのデュアルモデル 学校と現場実習」

報告1 スティナ・ヴァング・イリアス氏
スティナ・ヴァング・イリアス氏は、デンマークの職業訓練システムにおける政治的アクターとその役割について報告した。職業訓練システムにおける政治的アクターとして、全国レベルでは「教育省」「中央職業訓練委員会」「専門業種委員会」が設置され、地方レベルでは「地域教育理事会」が設置されている。
全国委員会である中央職業訓練委員会は経営者団体、労働組合、職業専門学校組織、地方自治体、学生組織から選出されたメンバーから構成されている。その役割として、職業訓練プログラムの設置や廃止について教育省に提言すること、そのために必要な労働市場の分析などもする。専門業種委員会は職業訓練プログラムの内容、構成、決定に関して責任を負い、カリキュラムの策定や改訂にも責任を負う。また、労働市場のニーズの変化を把握、特定して教育省に報告書を作成すること、現場実習を行う企業の認定などもする。地域教育理事会は職業訓練に係る地域レベルでの調整をする。それは地域の状況や目標をカリキュラムに反映させることなどである。
以上のように職業訓練プログラムの開発、管理には多くのアクターが密接に連携していることが紹介された。
全国委員会である中央職業訓練委員会は経営者団体、労働組合、職業専門学校組織、地方自治体、学生組織から選出されたメンバーから構成されている。その役割として、職業訓練プログラムの設置や廃止について教育省に提言すること、そのために必要な労働市場の分析などもする。専門業種委員会は職業訓練プログラムの内容、構成、決定に関して責任を負い、カリキュラムの策定や改訂にも責任を負う。また、労働市場のニーズの変化を把握、特定して教育省に報告書を作成すること、現場実習を行う企業の認定などもする。地域教育理事会は職業訓練に係る地域レベルでの調整をする。それは地域の状況や目標をカリキュラムに反映させることなどである。
以上のように職業訓練プログラムの開発、管理には多くのアクターが密接に連携していることが紹介された。

報告2 トマス・フェラン氏
トマス・フェラン氏はデンマークの職業訓練制度とデンマーク(労働市場)モデルについて報告した。
デンマーク職業訓練においては特に労使が大きな役割を果たしており、職業訓練の質の保証や財源の管理に関してソーシャルパートナー(労使)が協力し、多くの規定が労使協約によるものであることが示された。政府も職業訓練、労働市場の管理に大きな責任を負っている。デンマークの職業訓練制度の課題として「職業訓練志望者が少ないこと」「落第率の高さ」「熟練労働者の引退」「特定分野の熟練労働者の不足」「現場実習の受け入れ企業の不足」等が挙げられた。対策として「予算の増加」「基礎過程受講中の俸給」「人参と鞭の手法」「公立学校の改革」等が示された。
デンマークモデルについては、ソーシャルパートナーの役割の重要性が示され、同モデルが「団体交渉」「フレキシキュリティ」「三者合意」によって形成されていることが示された。これは、労働市場の規制には団体交渉が大部分を占めていることや、雇用の柔軟性と高いレベルの生活保障の両立、政労使が政策決定において密接に連携していることを意味する。
デンマーク職業訓練においては特に労使が大きな役割を果たしており、職業訓練の質の保証や財源の管理に関してソーシャルパートナー(労使)が協力し、多くの規定が労使協約によるものであることが示された。政府も職業訓練、労働市場の管理に大きな責任を負っている。デンマークの職業訓練制度の課題として「職業訓練志望者が少ないこと」「落第率の高さ」「熟練労働者の引退」「特定分野の熟練労働者の不足」「現場実習の受け入れ企業の不足」等が挙げられた。対策として「予算の増加」「基礎過程受講中の俸給」「人参と鞭の手法」「公立学校の改革」等が示された。
デンマークモデルについては、ソーシャルパートナーの役割の重要性が示され、同モデルが「団体交渉」「フレキシキュリティ」「三者合意」によって形成されていることが示された。これは、労働市場の規制には団体交渉が大部分を占めていることや、雇用の柔軟性と高いレベルの生活保障の両立、政労使が政策決定において密接に連携していることを意味する。

報告3 アント・ヴェスタゴー・ロウ氏
アント・ヴェスタゴー・ロウ氏はデンマークのデュアルモデルについて、その強みと課題、学校での座学と現場実習がどのように高い学習効果をもたらしているのかを報告した。この報告の特徴として、学習や実習を行う生徒の視点が盛り込まれていることがあげられる。
デンマークのデュアルモデルでは学校での座学が全体の三分の一、現場実習が三分の二を占めている。学校での座学が生徒に職業能力の基礎の獲得を、現場実習が実践に基づいた専門的職業能力の獲得をもたらす。そして生徒は資格を得ることで学校から雇用に円滑に移行できる。デュアルシステムの課題としては、学校と現場に係る様々なギャップがある。
生徒の視点について、学校で学んだ理論が現場実習で実践されることによって生徒の学習が促進された事例などが挙げられた。特に報告者は現場実習の効果を強調した。職業を実際に経験することによる、身体的、物質的な職業的専門性の感受や、責任を引き受ける感覚などが学習において重要であることが示された。
デンマークのデュアルモデルでは学校での座学が全体の三分の一、現場実習が三分の二を占めている。学校での座学が生徒に職業能力の基礎の獲得を、現場実習が実践に基づいた専門的職業能力の獲得をもたらす。そして生徒は資格を得ることで学校から雇用に円滑に移行できる。デュアルシステムの課題としては、学校と現場に係る様々なギャップがある。
生徒の視点について、学校で学んだ理論が現場実習で実践されることによって生徒の学習が促進された事例などが挙げられた。特に報告者は現場実習の効果を強調した。職業を実際に経験することによる、身体的、物質的な職業的専門性の感受や、責任を引き受ける感覚などが学習において重要であることが示された。

会場の様子
2024年4月24日(水)午後7時より、本学池袋キャンパス8号館2階8202教室において、公開講演会「公認会計士への道」(公認会計士制度説明会)が例年通り開催された。本年度も昨年度と同様に、対面とオンラインのハイブリッド開催となった。対面は15名程度の参加者であったが、オンラインを併せると延べ60名以上の参加者を得て盛況であった。

羽山友紀子氏の講演
まず、司会(小澤)及び郭洋春経済研究所長のあいさつの後、日本公認会計士協会東京会広報委員会委員で、本学文学部フランス文学科卒業された羽山 友紀子氏(公認会計士)から公認会計士制度の説明があった。羽山氏は「公認会計士の仕事と魅力」と題して、公認会計士の使命、監査・税務・コンサルティングといった公認会計士の専門分野と活躍フィールド、試験制度の概要等についてお話くださった。また最後に現役公認会計士の声として、監査業務が拡大していることや、海外でも活躍できること等、いかに公認会計士が魅力的な仕事であるかを熱弁し、後輩たちに試験への挑戦を促された。

金沢信二朗氏の講演
次に、公認会計士試験に本学経済学部経済学科在学中に合格し、2024年3月に本学を卒業され、現在、EY新日本有限責任監査法人に勤務されている金沢 信二朗氏から、合格体験談をお話しいただいた。特に、大学生活と資格試験勉強の両立、試験勉強の仕方、試験合格後の日常など、参加者にとってとても有益な内容であった。金沢氏は、公認会計士試験にチャレンジする後輩たちに向けて熱いエールでご講演を締めくくられた。

山田浩一氏の講演
最後に山田浩一氏(公認会計士・立教公認会計士会会長)から、ベテラン公認会計士の視点に基づく、公認会計士という職業の魅力についてお話くださった。この仕事には、巷に言われるような「AIに仕事を奪われる」ような未来はなく、ぜひともこの試験にチャレンジしてほしいと、学生を激励していただいた。
講演会終了後には、対面参加の学生とオンライン参加の学生から、多くの質問が寄せられた。10分の質疑応答時間を予定していたが、それを大幅に超過し、講師の先生方には時間の許す限り後輩たちの質問にお答えいただいた。本年度も監査業務の繁忙期と開催時期が重なってしまったが、後輩のために貴重なお時間を割いて本学までお越しいただいた講師の先生方と日本公認会計士協会東京会各位には、改めてお礼申し上げたい。
